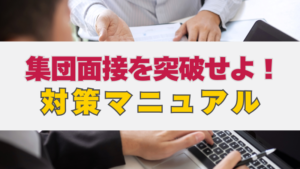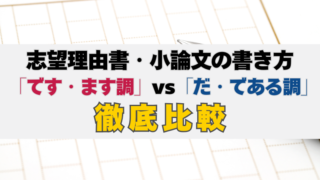
総合型選抜 志望理由書・小論文の書き方:「です・ます調」vs「だ・である調」徹底比較
こんにちは!KOSSUN教育ラボ教務担当です。
総合型選抜(旧AO入試)において、志望理由書や小論文は、あなたの思考力、表現力、そして大学への適性を評価する上で非常に重要な書類です。
これらの書類でどちらの文体、「です・ます調」と「だ・である調」を用いるべきか、多くの受験生や保護者の方が疑問に感じているのではないでしょうか。
この記事では、志望理由書と小論文に特化して、それぞれの文体の特徴、適切な使い分け、そして書く際の注意点を詳しく解説します。あなたの意図を正確に伝え、選考担当者に響く書類作成をサポートします。
1. 志望理由書・小論文における文体の重要性
志望理由書や小論文は、単に情報を伝えるだけでなく、あなたの個性や思考の深さ、大学への熱意を示すためのものです。文体は、これらの内容にニュアンスを与え、読み手に与える印象を大きく左右します。
- 「です・ます調」: 丁寧さ、親しみやすさ、真摯な姿勢を伝えやすい。
- 「だ・である調」: 論理性、客観性、アカデミックな印象を与えやすい。
どちらの文体が適切かは、書類の種類、大学・学部の求める人物像、そして記述する内容によって異なります。
2. 志望理由書における文体
志望理由書は、あなたがなぜその大学・学部を志望するのか、入学後に何を学びたいのか、将来どのような貢献をしたいのかを具体的に述べるものです。
一般的には、「です・ます調」を用いるのが基本とされています。
- 「です・ます調」が推奨される理由:
- 丁寧さと敬意: 大学の選考担当者に対して、敬意と丁寧な印象を与えることができます。
- 真摯な姿勢: 熱意や真剣さを伝えやすく、入学への強い意欲を示すことができます。
- 親しみやすさ: 自身の経験や思いを、比較的親しみやすい言葉遣いで表現できます。
例文(です・ます調):
「私が〇〇大学〇〇学部に惹かれたのは、〇〇という貴学の理念に深く共感したからです。高校時代の〇〇という経験を通して、私は〇〇という課題に関心を抱くようになりました。貴学部では、〇〇について専門的に学ぶことができると伺い、私の探求心を強く刺激されました。入学後は、〇〇先生のご指導の下、〇〇に関する研究に励み、将来は〇〇の分野で社会に貢献したいと考えております。」
例外:
一部の理系学部や、研究活動への意欲を強くアピールしたい場合など、内容によっては部分的に「だ・である調」を用いることも考えられます。ただし、その場合でも全体を通して文体が大きく乱れないように注意し、基本は「です・ます調」で統一するのが無難です。
注意点:
- 志望理由書全体を通して、文体を統一してください。「です・ます調」と「だ・である調」が混在すると、読みにくく、まとまりのない印象を与えます。
- 過度に感情的な表現は避け、丁寧な言葉遣いを心がけつつ、具体的な事実に基づいて記述しましょう。
- 熱意を伝えたいあまり、稚拙な表現にならないように注意し、適切な敬語を用いるようにしましょう。
3. 小論文における文体
小論文は、与えられたテーマに対して、あなたの知識、論理的思考力、分析力、そして客観的な考察を示すものです。
一般的には、「だ・である調」を用いるのが適切とされています。
- 「だ・である調」が推奨される理由:
- 客観性と論理性: 主観的な感情を排し、客観的な事実に基づいて論理的に議論を展開するのに適しています。
- アカデミックな印象: 論文としての形式が整い、知的な印象を与えます。
- 簡潔性: 無駄な装飾を避け、簡潔で力強い文章表現が可能です。
例文(だ・である調):
「現代社会において、〇〇という問題は深刻化の一途を辿っている。その背景には、〇〇という構造的な要因が存在すると考えられる。先行研究によれば、〇〇という事実が明らかになっている。本稿では、〇〇という視点からこの問題の本質を分析し、〇〇という解決策を提案する。」
例外:
大学や学部によっては、小論文においても「です・ます調」での記述を指示する場合があります。これは、大学の特色や求める人物像によって異なるため、必ず募集要項を確認し、指示に従ってください。
注意点:
- 小論文では、「だ・である調」を用いる場合でも、口語的な表現や砕けた言葉遣いは避け、客観的で厳密な表現を心がけましょう。
- 主張には必ず根拠を示し、論理の飛躍がないように注意深く議論を展開してください。
- 感情的な言葉や主観的な意見ばかりにならないように、客観的なデータや事実に基づいて論じるようにしましょう。
- 句読点の使い方、漢字の誤りなど、基本的な文章ルールをしっかりと守り、読みやすい文章を作成することが重要です。
4. 文体を選ぶ際の最終確認
志望理由書や小論文の文体で迷った場合は、以下の点を再度確認しましょう。
- 大学・学部の募集要項: 文体の指定がないか必ず確認してください。
- 大学・学部のウェブサイトやパンフレット: 大学の理念や教育方針、求める人物像から、どのような文体が好まれるか推測してみましょう。
- 過去の合格者の書類: 可能であれば、過去の合格者の書類を参考に、どのような文体が用いられているか確認してみるのも良いでしょう。
- 指導者の意見: 学校や塾の先生など、指導者の意見を聞き、客観的なアドバイスをもらいましょう。
5. 文体以上に重要なこと
文体の選択は重要ですが、それ以上に、志望理由書や小論文の内容そのものが重要です。
- 明確な志望動機: なぜその大学・学部で学びたいのか、具体的な理由を明確に記述しましょう。
- 具体的な学習計画: 入学後、どのような分野を学び、どのような研究に取り組みたいのか、具体的な計画を示しましょう。
- 将来の展望: 大学で学んだことを活かして、将来どのように社会に貢献したいのか、明確なビジョンを描きましょう。
- 論理的な構成: 説得力のある文章にするためには、論理的な構成が不可欠です。
- 独自性・オリジナリティ: 他の受験生との差別化を図るために、あなた自身の経験や考えに基づいた独自の視点を盛り込みましょう。
文体は、これらの内容を効果的に伝えるための「装い」のようなものです。まずは内容をしっかりと練り上げることが最も重要であることを忘れないでください。
KOSSUN教育ラボの活用
KOSSUN教育ラボは、小論文対策講座や個別指導、面接対策など、総合型選抜に特化した様々なサポートを行っています。
専門の講師があなたの個性や強みを引き出し、合格に向けて徹底的に指導します。
KOSSUN教育ラボのサポート体制
- 小論文対策講座: 基礎知識の習得から応用力養成まで、段階的に小論文の書き方を学ぶことができます。
- 個別指導: 自分の課題に合わせて、講師にマンツーマンで指導を受けることができます。
- 添削指導: 実際に書いた小論文を講師に添削してもらい、改善点を見つけることができます。
- 面接対策: 面接で聞かれる可能性のある質問を想定し、練習することができます。
- 出願書類添削: 志望理由書や自己PR文など、出願に必要な書類の添削を受けることができます。
- 情報提供: 総合型選抜に関する最新情報や大学の情報を手に入れることができます。
KOSSUN教育ラボからのメッセージ
志望理由書や小論文の文体選択は、あなたの意図を正確に伝え、選考担当者に良い印象を与えるための重要な要素です。
この記事で解説した内容を参考に、それぞれの書類の目的に合った適切な文体を選び、自信を持って作成に取り組んでください。
KOSSUN教育ラボでは、総合型選抜・学校推薦型選抜(AO入試・推薦入試)に特化した対策を行っています。
受験でお困りの方は、お気軽に無料個別相談会にお申し込みください。
※この記事は専門家による監修のもと執筆されています。

この記事を監修した人
西村 成道(にしむら・なるみち)
KOSSUN教育ラボ 副代表。総合型選抜(AO入試)のプロ講師として1,200名以上の塾生をサポート。特に書類選考の通過率は通算96.4%と業界トップを記録。難関大学を中心に、「評定不良」「実績なし」「文章嫌い」からの逆転合格者を毎年輩出。圧倒的な指導力と実績が受験生、保護者の間で話題となり、全国から入塾希望者が殺到している。著書、メディア出演多数。